18650リチウムイオン電池の良否の判断

Eサイクルバッテリーは18650のリチウムイオン電池で構成されています。
今回は中古の18650の良し悪しを判断する基準についてメモを残しておきます。
18650の選別の判断基準の参考になれば幸いです。
また、末尾には過放電してしまったバッテリーなど、再利用への模索も行っています。あくまで実験的な段階ですが、参考になれば幸いです。
また、18650電池は広く組電池の単電池として使われており、パナソニックやサムソンなど多くのメーカーから組み込み向けに供給されています。
(単電池での販売は基本的にメーカーが認めていない場合が多いです)
1.内部抵抗値を評価する必要性
廃棄のEサイクルバッテリーを活用した蓄電池ユニットの試作を行おうと思っていました。
一般に組電池を組む場合は極端に新しいものと、劣化したものを組み合わせると、BMSでバランスを取る時に、劣化したものが基準になります。
それだと、劣化していない方の電池は本領発揮できません。
そこで、電池の劣化具合をそろえるため、内部抵抗値をある程度そろえて、組みたいと思っていますが、この内部抵抗値の判断基準がよくわからない。何mΩくらいを目安にしたら良いのか、どういうふうに評価したら良いのか、調べたので、メモしておきます。
2.充電評価方法

・ステップ 1
充電評価を行う前にリチウムイオン電池を周囲温度 25±5℃で 0.2 C の定電流で放電終止電圧まで放電する。
リチウムイオン電池を周囲温度 25 ±5℃で 1~ 4時間静置する。
・ステップ 2
電池電圧が 3 V以下の場合、0.1 Cで充電を行う。
3 分以内に電池電圧が 3 V 以上にならなかった場合は電池不良と判断し、充電評価を終了する。
・ステップ 3
リチウムイオン電池を周囲温度 25±5℃で 1 Cの定電流で充電する。
・ステップ 4
電圧が 4.2 V に到達したら定電圧に切り替え、充電を継続する。
・ステップ 5
充電電流が 0.05 Cに到達したら充電を終了する。
充電時間が 2 時間 30 分経過した場合は異常と判断し、充電評価を終了する。
電池温度が 45℃に到達したら異常と判断し、充電評価を終了する。
内部抵抗は状況によって変化する
リンク先のレポートがわかりやすく、参考になった。
中でも、放電時の内部測定値の推移もとても参考になった。
わかったことは電池の内部抵抗は一定ではなく,状況によって変化するということ。
参考資料:機械屋のためのリチウムイオン電池活用入門
以下、重要そうなところを簡素にまとめて抜粋。
電池は繰り返し使用すると徐々に劣化していく。
劣化が進むと内部抵抗が増加し,新品のときの性能を発揮できなくなる。
また,電池の容量が少ないとき,環境温度が低いとき,放電電流が大きいときにも内部抵抗は増加する。
電池の劣化以外の内部抵抗の増加は一時的なものであり,状況が解消されれば回復する。
そのため,一定の条件で内部抵抗を測定すると電池の劣化具合が分かる。
3.では一定の条件での内部抵抗の測定方法とは?

内部抵抗測定は交流法と直流法の 2 種類の測定方法がある。
【交流法】
交流法は電池に一定の周波数の交流信号を印加し,測定した実効電流及び電圧から抵抗値を求める方法。
【メリット】
交流法は電池の容量を消費することなく内部抵抗の測定が可能である。
しかし,高い周波数を使用するため,測定者による測定誤差が生じることがある。
【直流法】
直流法は電池に僅かに電流を流したときの電圧と大きな電流を流したときの電圧を測定し,その電圧の変化から抵抗値を求める方法である。
【メリット】
交流法と比べ測定者による測定誤差が生じにくく,放電評価に使用する電子負荷装置があれば,追加機材を必要とせずに内部抵抗を測定することができる。
直流法の内部抵抗の測定方法
電池を 0.2 C の一定電流(I1)で放電し、30±0.1秒後に放電電圧 U1 を測定し、記録する。記録後、直ちに放電電流を 1.0 Cに増加させ(I2)、5±0.1秒後に放電電圧 U2 を測定し、記録する。
なお、測定は通電による電圧降下の影響を受けないよう 4端子法またはそれに準じた方法で行う。
電池の直流内部抵抗Rdcは,次の式によって求める。
Rdc(Ω)= (U1-U2)÷(I2-I2)
ICR18650・NCR18650Bの内部抵抗の基準はどれくらいか?

では、僕が使うICR18650・NCR18650Bの内部抵抗の基準はどれくらいか?
充電器で充電して、内部抵抗値が出てくるので、それを基準に平均化してもよいと思うが、一応、メーカーのデーターシートなりを探してみることにした。
以前使用していた、サムスン製のICR18650も、現在使用しているパナソニック製のNCR18650Bも性能表によれば、100mΩ以下で製品として流通させているようだったので、これを1つの参考値とすることは良いのかもしれない。
ICR18650データーシート(RSコンポーネンツ)
NCR18650B(http://www.batteryonestop.com/)
4.簡易的な内部抵抗の測定と充電器
私は複数の電池を一度に充電したいと考え、こちらの充電器を使用しています。
同時に8本充電できます。
また、内部抵抗値も自動で表示してくれますので、上記の計算を行わずともある程度の目安がとれると思います。
過放電電池の充電実験
実験的にではありますが、過放電した18650電池も充電が出来、その後もLEDハンドライト等で使用可能で、再度の再充電も可能でした。
コメント欄に大変興味深い内容が以下のようにありました。
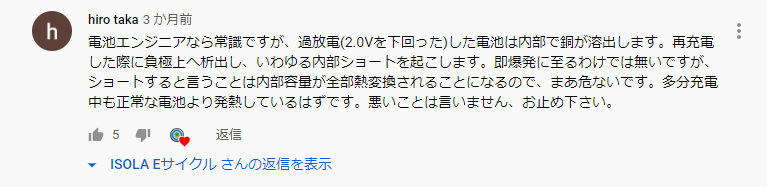
仮に銅の溶出減少により、セル内部がショートをした場合は、導通するということになると仮定する。
上記の充電器では、それを自動判別し、充電を開始しない機能がある。
問題は、この銅の溶出現象がどこまで、ショートにつながることかということ。
微妙にしかショートしておらず、発熱の原因程度にとどまる場合は、この内部ショートの兆候だと見るとすると、充電中にそれぞれの電池の温度を監視し、40℃以上などの異常があった場合には測定し、その電池の充電をキャンセルし、使わないようなシステムを組み込めば、安全で良い充電器に一歩近づけると言えるのではないだろうか?
2020/12/23追記
上記の考えを元に、200円のコストで、3分の作業時間で充電時の温度監視を実現できるカスタマイズ方法を考案しました。
2021/08/27 追記
上記の考えを元に、発熱電池=劣化電池という図式を仮定し、1本あたり0.5円のコストで発熱している電池を見分ける方法を構築しました。
マスキングテープと、フリクションライトというペンで実現できるため、どなたでも簡単に劣化電池の兆候を見分けることが出来ます。
今後
今後、バイメタルなどのサーモスイッチを充電回路に組み込み、充電池の温度が設定値以上になると、充電回路のカットオフをさせようと思います。
→2020年12月に実現しました。
また、上記のフリクションライトを使う手法は低コストで、なおかつ作業時間がほとんどいらないため、このフリクションライト法で見分ける方法をベースにして、リユース電池を運用していきたいと思います。
今後、さらに、氷点下でも充電を開始しないようなカスタマイズを、模索したいと思います。
このページでは、主に、Eサイクルバッテリーの単電池でもある、18650電池について記載していきます。これからも追記していく予定です。
🍀2011年から電動バイク製作 ISOLA株式会社🍀
新車、中古車、世界に一台だけのオーダーメイドバイクのご注文承ります。
お気軽にお問い合わせください。
————————————–
問い合わせフォームはこちら。
LINEでのお問い合わせも歓迎します!
このURLから、友達追加出来ます。
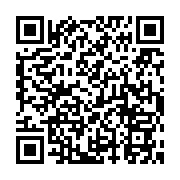




2件の返信
初めまして、大変勉強になりました。仕事で充電式電動工具を使用する機会が増えまして、その中でどうしてもバッテリーパックの交換が必要になります。(専用充電器の充電不可表示)そこで、分解点検してみると18650が4本から8本も使われているではありませんか、「これ全部がダメなのか?」と疑問に思い、試行錯誤を繰り返している次第です。今回はリチュウムイオン電池1865ですが、ニッケル水素充電電池(単2タイプ)やニッカド充電電池でも0Vからの復活方法はあるのでしょうか?
コメントありがとうございます。m(_ _)m
お役に立てて幸いです。
そうですね、リチウムイオン電池は複数本が直並列の組み合わせで使われていることが多いです。
そして、北澤さんのように充電不可で廃棄されてしまうことも多々あります。
しかし、実際にはその複数本の中のいくつかの電池が悪いだけで、ほかは使えるということが結構あります。
ただ、充電電流値の差異や容量の差異、BMSの規格などにより、いろんな電池を混ぜて使うことはあまり推奨はできませんので、頭に入れておくと良いと思います。
ニッケルとニッカドの復活方法はあるのかについては、すいません、私はそちらは詳しくありません。
ニッカドはトリクル充電など聞いたことはありますし、ニッケル水素電池も復活できるようですが、ケースバイケースだと思います。
検索してみるとたくさん記事は出てきますので、ご覧になってみてください。